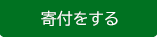酪農学専攻 修士課程 一覧 (2026年1月現在)
【作物生産科学】
| 研究指導分野 | 指導教員氏名 | 研究内容 |
|---|---|---|
| 土壌植物栄養学 | 教 授小八重 善裕 |
圃場における物質循環を作物栄養学の視点で捉え、栽培に生かす研究を行う。特に菌根などの共生システムを分子生物学的手法を用いて理解する。 |
教 授澤本 卓治 |
土壌を中心とした物質循環を研究対象としており、具体的には土壌やふん尿処理過程から発生する温室効果ガスの動態や土壌中の養分の挙動について研究を行う。 | |
| 病理・害虫学 | 教 授園田 高広 |
アスパラガス病害の発生生態の解明及び病害抵抗性育種に関する研究に取り組む。 |
教 授薦田 優香 |
農作物や牧草などに感染するウイルスを主な研究対象とし、生化学的及び分子生物学的手法を用いて、植物とウイルスとの相互作用やウイルス感染・増殖機構の解明を目指す。 | |
准教授中平 賢吾 |
持続可能な農業害虫の防除体系の確立を目指して、害虫と天敵の生活史や行動等の基礎生態の解明や、農業現場における害虫の発生メカニズムの解明、天敵昆虫の利用法の開発等に関する研究を行う。 | |
| 飼料作物学 | 教 授三枝 俊哉 |
寒地における資源循環型の持続的な草地管理および粗飼料生産技術の確立を目指す。 1.主要草種の生育特性解明 2.草地の草種構成制御 3.草地飼料畑の養分動態解明 |
教 授義平 大樹 |
飼料作物(トウモロコシ、牧草、麦類)と食用作物(麦類、豆類)における多収と高品質を両立できる栽培技術の確立と、その乾物生産過程からみた要因解明について研究する。 | |
准教授林 怜史 |
作物(イネ、トウモロコシ、バレイショ)における多収、省力化、環境負荷低減栽培技術について研究する。 | |
| 植物遺伝学 | 教 授森 志郎 |
植物バイオテクノロジーを利用して園芸植物における生殖隔離の克服に取り組む。また、寒冷地特産園芸植物の生理生態的特性を明らかにし、高品質栽培技術の確立を目指す。 |
教 授我妻 尚広 |
圃場での雑草や生態系での野生植物の営みを分子生物学的な手法で明らかにし、それらの雑草や野生植物集団の遺伝構造を推測し、伝来や拡散過程を研究する。 | |
准教授岡本 吉弘 |
自殖性作物、特にイネの半数体育種法における諸問題に取り組む。 1.葯培養効率の技術改善 2.葯培養法以外の半数体育種法の確立 3.葯培養効率の遺伝子マッピング 4.DHLsやRILsなどのイネ実験系統群の作出 |
|
| 酪農機械学 | 准教授石川 志保 |
家畜排せつ物等バイオマスのエネルギー利用に関する研究や、家畜の快適性と作業効率向上のためのスマート統合システムを開発し、家畜・ヒト・環境に優しい新たな畜産経営システムの構築を目指す。 |
家畜生産科学
| 研究指導分野 | 指導教員氏名 | 研究内容 |
|---|---|---|
| 家畜繁殖学 | 教授今井 敬 |
1.ウシ体外受精胚における発生率向上及び受胎性評価技術に関する研究 2.ウシ雌雄産み分け技術の高率化に関する研究 3.家畜胚の新しい生産技術の開発に関する研究 |
教授堂地 修 |
1.ウシ胚の効率的な生産方法の開発 2.ウシ卵子及び胚の超低温保存技術の開発 3.胚移植の受胎率向上と有効利用 4.高泌乳牛の繁殖生理の特性 5.牛の繁殖管理技術の向上 |
|
准教授西寒水 将 |
1. 乳牛および肉牛におけるゲノミック評価と繁殖技術 (人工授精、受精卵移植、体外受精)を併用した効率的な牛群整備および経済的高能牛の生産に関する研究 2. 人工授精および受精卵移植の受胎率向上に関する研究 3.食品加工副産物等の未利用資源利用によるエコフィードを活用した肉牛の飼養コスト低減技術の研究 |
|
| 遺伝・育種学 | 教 授 天野 朋子 |
1.家畜における乳と肉の生産に関わる遺伝子の研究 2.家禽における卵と肉の生産に関わる遺伝子の研究 3.家畜と家禽の適切な管理に関わる抗病性や繁殖能力、気質などの形質を制御する遺伝子の研究 |
准教授 増田 豊 |
家畜の経済諸形質を遺伝的に改善するための手法について研究する。 1.遺伝的能力予測のための統計モデルの構築 2.ゲノム情報等を用いた育種技法 3.データ解析のためのソフトウエアの開発 |
|
| 家畜栄養学 | 教 授 菊 佳男 |
1.牛の乳房炎の診断、治療および予防に関する研究 2.牛の乳房炎に対する抗菌薬治療の代替法に関する研究 |
教 授 中辻 浩喜 |
土地利用型乳肉生産システムを土-草-家畜を巡る物質循環として捉え、飼料のエネルギー利用効率および単位土地面積当たりの家畜生産量の観点から総合的に評価する。 | |
教 授 山田 未知 |
豚や鶏におけるエコフィードの活用法や給与飼料が十分活用されるような飼養環境の改善について研究を行う。また、養豚においては効率的な子豚生産のために、その繁殖性改善のための研究も併せて行う。 | |
講 師 土井 和也 |
自給飼料を主体とした反芻家畜の飼養管理を目指して、粗飼料や粕類のサイ レージ調製に関する研究や、放牧地にて加速度センサーを用いて摂取量を把握する研究を行う。 | |
| 家畜管理学 | 教 授 森田 茂 |
家畜の動作・活動(採食行動、休息行動、人に対する反応)を解析するとともに、家畜の社会行動から家畜同士の関係を把握することで家畜の習性に配慮し、洗練化された飼養管理技術の構築を目指す。 |
教 授 山田 弘司 |
人と動物の関係学の研究として、アニマルセラピーや乗馬療法の効果、人と ペットの関係調査、動物のストレス反応や性格・気質測定、動物園動物の展示と行動調査を行う。 | |
准教授 猫本 健司 |
ふん尿の循環利用・窒素収支に関する研究、搾乳関連排水の低コスト処理、温室効果ガスの発生実態などを検討する。今後は「実践」にふさわしい新たなテーマも取り組む。 | |
| 酪農生物化学 | ※未定 | – |
酪農情報学
| 研究指導分野 | 指導教員氏名 | 研究内容 |
|---|---|---|
| 酪農経営情報学 | 教 授 吉野 宣彦 |
酪農専業地帯の農協の業務データ等をデータベースに構築し、逐次経営分析を可能にするプログラムを開発して研究に利用する。 1.酪農経営における収益性格差の要因 2.草地更新における経済効果の形成条件 3.放牧酪農における高収益の確保条件 |
| 農業経営学 | 教 授 日向 貴久 |
1.畜産経営における、経営管理・経営計画に関する研究 2.持続的な農業に向けた生産者の意思決定に関する研究 3.持続的な農業を推進するための社会条件に関する研究 |
教 授 吉岡 徹 |
1.農業経営における、経営戦略の立案と実践方法について 2.地域営農システムの展開条件と方向性に関する研究 3.農業支援システムの成立要件と発展方向に関する研究 |
|
| 酪農政策学 | 教 授 井上 誠司 |
地域農業のシステム化並びに地域農業振興計画の有効性に関する研究を行う。 |
教 授 小糸 健太郎 |
1.酪農の生産性に関する研究 2.農家の技術選択に関する研究 3.食品廃棄物・副産物利用の現状とその利用に関する研究 |
|
教 授 小林 昭博 |
農村と都市に通底する社会的・文化的問題を聖書とキリスト教思想に基づき応用倫理学の観点から読み解く。 1.ジェンダー研究、セクシュアリティ研究、クィア研究 2.平和研究、人権研究、生命倫理学 3.動物の福祉、動物の権利、自然との共生 |
|
| 農業市場学 | 教 授 糸山 健介 |
農畜産物の流通システムと結節点としての農業協同組合の機能に関する研究 |
環境共生学
| 研究指導分野 | 指導教員氏名 | 研究内容 |
|---|---|---|
| 野生動物学 | 教 授 佐藤 喜和 |
北海道を代表する野生動物であるヒグマを中心に、その生態を理解し、人間との軋轢を最小化するため、野外調査から室内実験、データ解析まで様々な手法を用いた研究を行う。 |
准教授 伊吾田 宏正 |
野生動物管理の重要な要素である狩猟について、その生態学的・社会的役割を追求するため、狩猟に関する動向や意識、狩猟鳥獣の生態および効率的捕獲手法等を研究する。 | |
准教授 鈴木 透 |
野生動物・生物多様性と人間社会との共生を図るために、保全生物学・景観生態学的なアプローチを用いた基礎的・応用的な研究を行っている。 | |
准教授 立木 靖之 |
地域の生物多様性と社会の境界線上に生じる軋轢の解決を目的に、国内外のフィールド調査で収集された「事実」に基づき、両者にとっての利益を見出し、共存する方法を探求する。 | |
准教授 原村 隆司 |
野生動物の行動や生態に関する研究を行っており、研究対象とする生物は、主として両生類または昆虫類の各種で基礎的研究に重点をおいて調査する。 | |
講 師 伊藤 哲治 |
野生動物の生態・生息状況を考慮した野生動物管理を、広域的・局所的に行っていくための知見を得ることを目的として、フィールド調査により得られた情報・試料を用いて、様々なアプローチにて調査・研究を行う。 | |
講 師 松林 圭 |
昆虫を中心とした無脊椎動物の多様性創出および維持機構を、生態遺伝学的手法を用いて解明する。指導分野は、進化生態学、行動生態学、分類学、分子集団遺伝学、量的遺伝学、形態学が主だが、希望すればゲノミクスや数理解析、化学分析まで可能。 | |
准教授 森 さやか |
野生動物の生態や行動、進化についての基礎的な研究を基盤としつつ、保全に関わる応用的研究にも取り組む。野外調査を重視するが、GIS解析、DNA解析などの手法も用いて研究を行っている。主要な研究対象は野生鳥類。 | |
| 国際環境情報学 | 教 授 星野 仏方 |
主にアジアの生態・環境となりわいの長期変動のモニタリングや解析、研究を行なっている。 |
准教授 小川 健太 |
衛星、航空機、無人機からの計測(=リモートセンシング)、GIS、GPS等を用いた森林や農地のモニタリング、気候変動の予測、環境政策の立案等への情報活用に関する研究を行う。 | |
講 師 吉村 暢彦 |
GIS、GPS、リモートセンシング技術を用いた森林管理や防災、観光等の分野における人の活動の評価手法についての研究を行う。 | |
| 地球環境保全学 | 教 授 中谷 暢丈 |
環境中における生元素や有害物質の生物地球化学的循環過程の解明とその人的相互作用の評価、生物学的・化学的手法を用いた環境評価手法の開発に関する研究を展開する。 |
教 授 保原 達 |
陸上生態系内の現象に潜む目に見えない仕組みや原因などについて、生物と環境双方の共通項である『物質』を頼りに分析・解明している。 | |
教 授 吉田 磨 |
1.地球温暖化に関する国内外フィールド観測と国際精度分析 2.生物地球化学的物質循環と地球環境変化の解析 3.フィールド観測を用いた持続可能な農業・漁業・観光業創造 |
|
教 授 馬場 賢治 |
気象学や気候学、海洋学を中心として、それらに関係する様々な分野の研究を行っている。観測やシミュレーション解析によるデータを利用して、現実と理論の双方から場の理解や解明を目指す。 | |
教 授 遠井 朗子 |
環境条約の実効性を日本について、国内法における環境条約の受容の程度を実証し、評価することにより検討している。特に生物多様性・自然保護関連条約に焦点を当てている。 | |
准教授 松山 周平 |
自然植生や希少植物の保全・管理に関する問題に取り組みながら、その問題の中にある植物の生態や進化に関する研究を行っている。 | |
講 師 千葉 崇 |
1.環境指標種群の検討 2.珪質殻を持つ微生物の化石化過程の解明 3.沿岸域における古地震・古津波研究 4.人為汚染などによる表層環境の急変とその後の遷移過程の解明 5.遺伝子と化石記録に基づく移入微生物の特定 |